障害者雇用がまだ進んでいない企業に話を聞くと「障害の方を雇用する環境が整っていない」と話される企業が多く、「多額のコストを掛けて環境を作っている」というイメージが選考していることもしばしば
実際に雇用をしている企業で多額のコストをかけて環境を整えるケースは多くなく
大企業や特例子会社ぐらいかと思います。
では障害のある方を雇用する上で必要な環境とはどういったものなのか解説していきます。
- バリアフリーとユニバーサルデザインと配慮の違い
- 事例を元に障害別の環境づくり
- 環境を整えるときの注意点
合理的配慮の考え方
障害者を雇用する際に、メインとなる課題として「合理的配慮」というものがあります。これは環境設定と大きく関係するものとなります。
合わせて障害者の環境を作ると考えたときに「バリアフリー」や「ユニバーサルデザイン」といった言葉も出てくると思います。
まずはこの3つ言葉の定義から説明していきましょう。
バリアフリー
障害のある方や高齢者などの障壁となるものをなくした環境が「バリアフリー」です。
わかりやすいもので言えば、スロープ・手すり・点字などすべての障害のある方とはいかないまでも、多くの障害がある方に利用しやすい環境を言います。
ユニバーサルデザイン
障害の有無だけでなく、性別、年齢などすべての方が利用しやすい環境を目指すのが「ユニバーサルデザイン」と言います。
わかりやすいものでいえば自動ドア・多目的トイレ・音声案内など万人とまで言わなくても多くの方が使いやすい環境のことを言います。
合理的配慮
合理的配慮は、特定の障害のある方に合わせて、社会的な障壁をなくしていくことを言います。
- 知的障害の方に合わせて指示書にルビをふる
- 聴覚障害の方に合わせて筆談での会話をする
といった、特定の障害に合わせた環境を設定することが合理的配慮です。
3つの環境の違い
「バリアフリー」、「ユニバーサルデザイン」、「合理的配慮」の大きな違いは、対象の分け方にあります。
バリアフリーとユニバーサルデザインは、多くの方を対象として使いやすい環境を目指していくものです。
しかし合理的配慮は、特定の個人に対して環境を設定をするものになります。
バリアフリーで手すりをつけたとしても、聴覚障害の方を雇用した時は、別の環境を設定する必要がある
障害者雇用では、バリアフリーではなく、合理的配慮が義務になります。
雇用をする予定又はしている方に合わせて、仕事ができる環境を作ることが求められています。
そのため対象者と相談の上、企業側に無理が出ない範囲で折衝することが重要なプロセスとなります。
働きやすい環境を作るための2つの視点
環境を作るに当たっては、下記2つの環境を作ることがポイントとなってきます。
- 物理的な環境整備
- 人的な環境整備
物理的な環境整備
環境を作るイメージのほとんどは、この環境の整備だと思います。
- エレベーター、エスカレータ
- スロープ
- 障害者用のトイレ
- 点字、アラーム
- 作業マニュアル
など
建物や設備そのものを整えていくことが物理的な環境です。
主に身体障害の方を対象とすることが多いですが、他にも知的障害の方にも有効なものもあります。後ほど具体例を使って説明いたします。
人的な環境整備
職場内での障害に対する理解を深め、対応できるメンターを作ることも重要な環境です。
- 相談できるメンターを作る
- 内部でも外部でもジョブコーチを依頼すること
- 社内研修をして障害理解を深める
など
特に発達障害、精神障害、知的障害の方々にとっては、物理的な環境より人的な環境の方が重要な要素になってきます。
では障害の種別ごとにどんな環境整備が必要なのか見て行きましょう。
事例から見る環境設定
簡単な事例を元に身体、知的、精神、発達の4つの種別で解説していきます。
対応の例は人や環境によって異なります。参考程度にご検討ください。
身体障がい:物理的90% 人的10%
身体障害をお持ちの方には、物理的な環境を整える事が求められます。
一概に身体障害といっても一括りには出来ず、障害の状態によって必要な環境は変わってきます。
事例1
車いす利用の方が事務職に入社するもオフィスに段差が多く、
通路も狭いため一人でデスクに行くことが出来なかった。

- 車椅子でも移動ができる動線の確保、簡易スロープなどの設置
- 環境を整えられない場合はテレワーク勤務や別スペースの確保
事例2
聴覚障害の方が、工場にて軽作業の業務をすることになったが、休憩のチャイムが聞こえない
- バイブ機能や光などを使ったアラームを使う
- 周囲から声を掛ける
知的障がい:物理的40% 人的60%
知的障害をお持ちのは、
文章の読み書き、計算、記憶、意味理解といった部分が課題になることが多いですが、人によって得意な事、苦手な事は違います。
どんな事が苦手で、何をしたら改善できるのか、をポイントに環境を作っていく必要があります。
事例1
マニュアルに漢字が多く、読めない
- ルビをふる
- 写真や画像を中心のマニュアルにする
- マニュアルではなく口頭と実践で指導する
事例2
人の顔と名前が一致しないことや物の場所を覚えられない
- 名札をつける
- メンターを一人に絞る
- 物の場所にラベルを貼る
- 業務をひとつずつ習得する
事例3
入社書類の内容が理解出来ないまま、入社したためトラブルが起こる

- 支援機関や家族などに同席してもらう
- 書類にルビをつける
特に社会的なルールや暗黙のルールみたいなことに関しては、いきなり理解をしていくことは難しいです。そのため、メンターをつけることは必要な環境設定となります。
精神障がい:物理的10% 人的90%
精神障害をお持ちの方に対しては、人的な環境を整えることが重要です。
身体には問題のない方が多く、メンタル面のフォローや一人ひとりに向き合って対応する事が最も大切な環境の作り方になります。
事例1
自分の評価が低いと感じており、定期的に不安が強くなる
- 定期的に面談をして評価を返す時間を作る
- 評価表など目でわかる評価を作る
事例2
定期的に気分の波があり、集中が続かなくなることがある
- 1~2時間ごとに5分程度の休憩時間を設ける
- 最低作業量を設定して作業が終わったら退社できるようにする
- 最初から業務を設定しすぎない
こうしたメンタルの不調に関しては、メンターが一人で担当すると担当者の負担が大きくなりがちです。
そのため、関係機関や病院などとの連携は必要だと考えたほうがいいでしょう。
精神障害について詳しくまとめた記事はこちら
発達障がい:物理的30% 人的70%
発達障害の方に関しては、得意と苦手なことがはっきりしていることが多いです。
そのため、一人ひとりの特性にあった仕事の環境を作ることで、力を発揮できるようになる方も多いです。
事例1
事務職に入社するも電話応対が苦手で退職を検討している。

- 電話応対を外して他の業務に専念する
- 電話応対は継続するなら社内だけorトークスクリプトの作成をする
- 電話応対の練習を何度かしてから徐々に慣れていく期間を作る
事例2
会話が苦手でどのように声を掛けたらいいのかわからず、報連相が出来ない。
- メモを渡すことからスタートしてみる
- 声の掛け方やタイミングを予め決めておく
- 声を掛ける人を決めておく
環境を整える上での4つのポイント
ここまで環境の事例をもとに対応例をお伝えしましたが、実際は本人に合うかトライアンドエラーで環境を変えていく必要があります。
その際の意識しておくポイントを4つお伝えします。
1.やりすぎない事
2.対象者に合わせる事
3.出来るだけ少額に出来る工夫をする事
4.誰もが納得できる環境はない
やりすぎないこと
すべての要望に応えようとして環境を整えると、職場の負担が大きくなり結果的に現場に負担がかかりすぎてしまいます。
合理的配慮は話しを聞いて話し合いをすることが義務であり、全てを対応することがいいのではありません。
やりすぎてしまうような環境は作らないことが継続雇用のポイントです。
対象者に合わせること
前述していますが、障害の特性や症状などによって配慮してほしいことは違います。
先回りの準備をするよりも面接や話し合いを重ねて、何をしてほしいのかを確認してから環境を整えるようにしましょう。
出来るだけ少額で工夫をする
はじめから多額のお金を使って、環境を整える必要はありません。
いきなり大きなコストを伴う改修をすることは、リスクが大きくなるためおすすめしません。
最初は出来るだけ少額で出来る工夫から検討してみましょう。
ただし、どうしても環境を整える必要がある場合は、助成金などもありますので合わせて検討することをおすすめします。
誰もが納得できる環境は無いことを知る
よく言われる例え話ですが
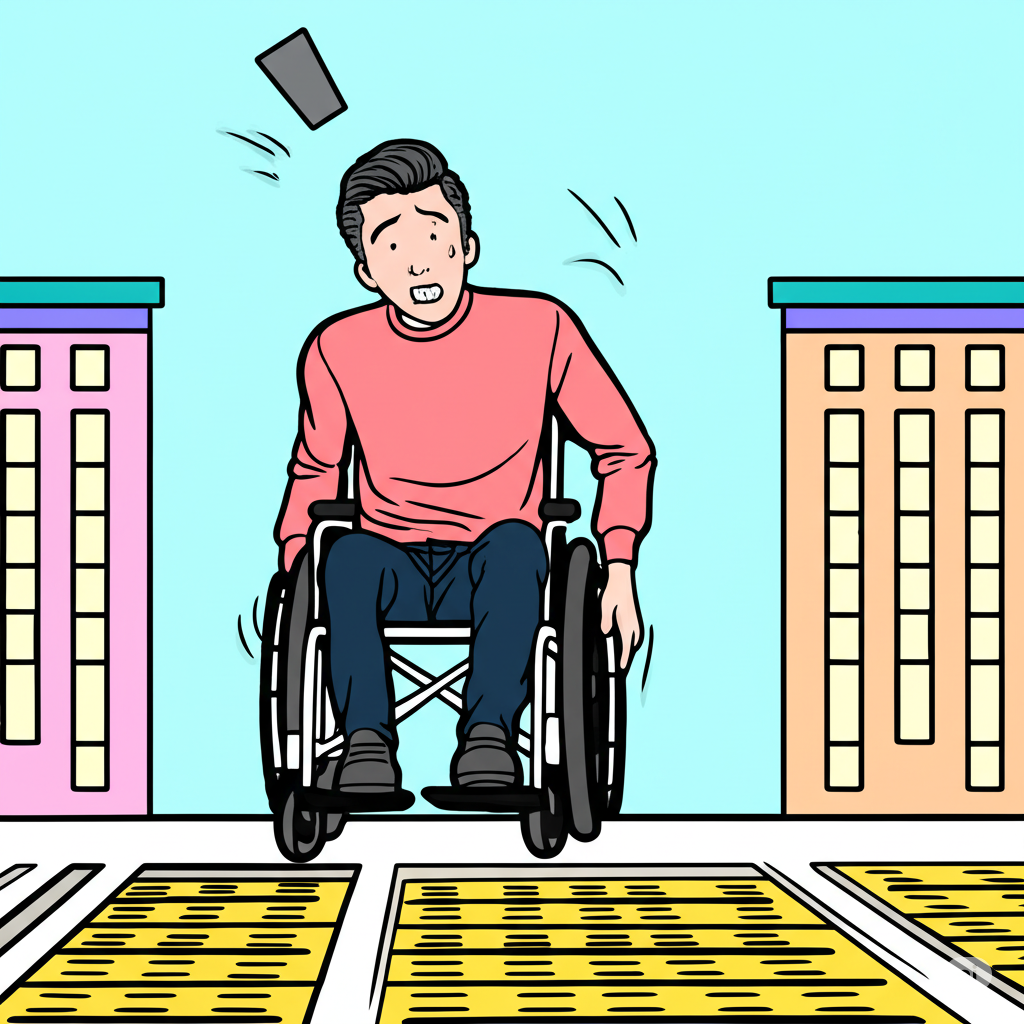
歩道にある点字ブロックは視覚障害者の方にとっては道になりますが、
車いすのユーザーにしてみれば道の妨げになることがある。
考える視点を変えると配慮が配慮ではなくなります。
万人受けする環境はないと考えて、何を目的に整備するのかを明確にすることが大切です。
環境についての相談場所
最後に働きやすい環境を整えるための相談先をご紹介します。
障害者職業センター
各都道府県に設置されている、企業向けの障害者の雇用に関する相談窓口です。無料で企業に対してのアドバイスや情報提供をしてもらえます。
また「ジョブコーチ」という職場適応をサポートする役割も担っているため、職場定着に関するご相談も可能です。
詳しくはホームページをご覧ください↓↓
障害者雇用コンサルタント
同じく障害者雇用のアドバイスから代行まで幅広く対応しています。
こちらは有料にはなりますが、環境に限らず求人出しから職場定着までアドバイスいただけます。
ご興味のある方がいらっしゃれば、私も運営をしておりますので、ご検討ください。
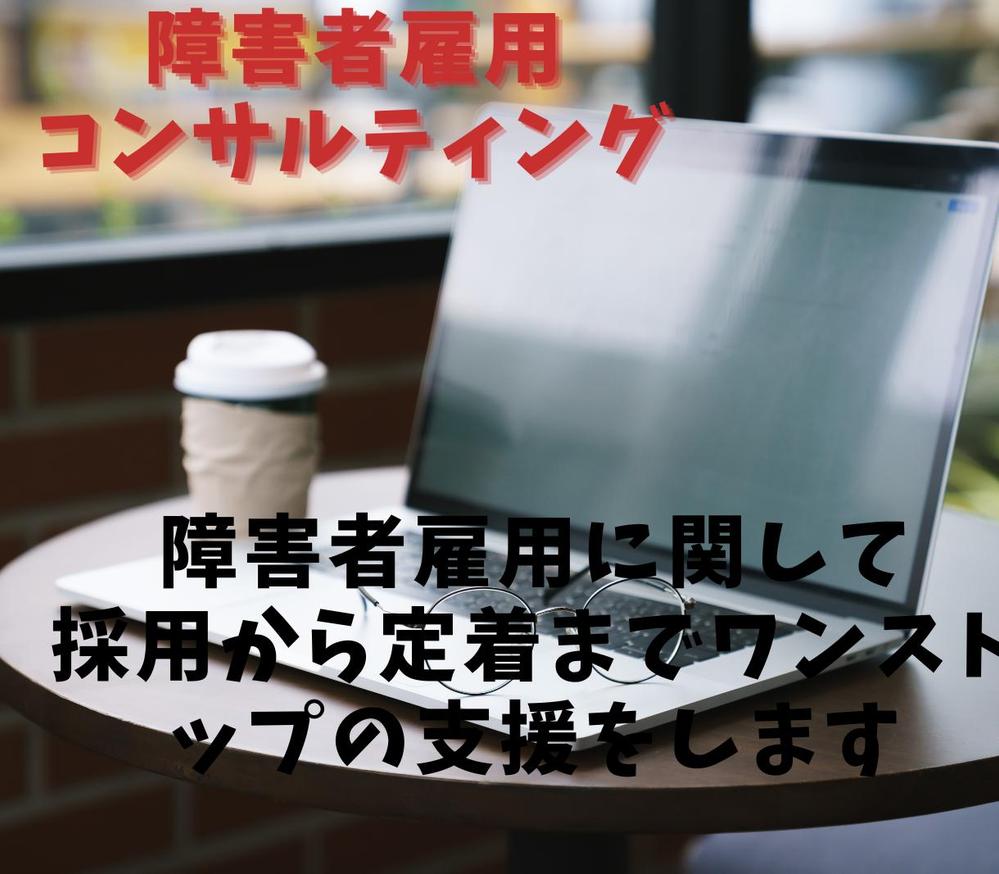
まとめ
・環境を整えるためには2つの視点がある
・身体障がいでは物理的環境を優先に整える
・精神障がいでは人的環境を優先に整える
・知的、発達障がいではバランスを見ながら整える。
環境を作るにあたっては、配慮することも大切ですが、既存のスタッフや運営に関しても考える必要があるため労力の必要な作業になります。
ただ、環境を作ることを怠るとどこかでひずみが出てしまい長期の雇用が難しくなることも・・・
難しいときは、相談機関に頼ることも必要だと思います。
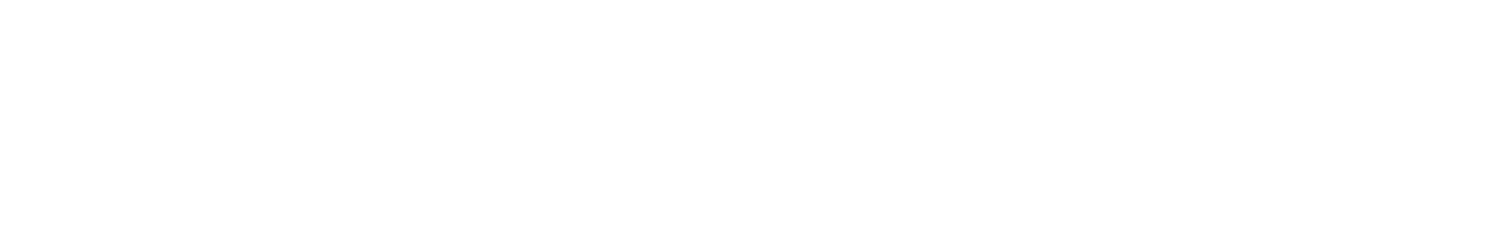








コメント